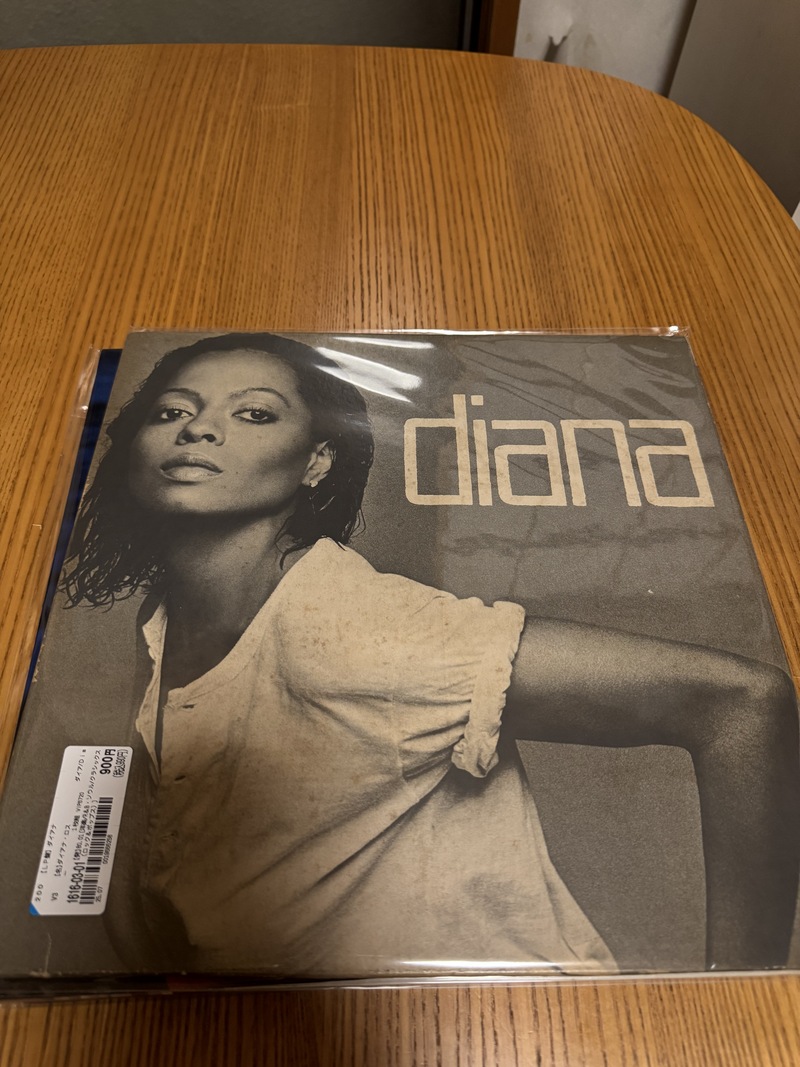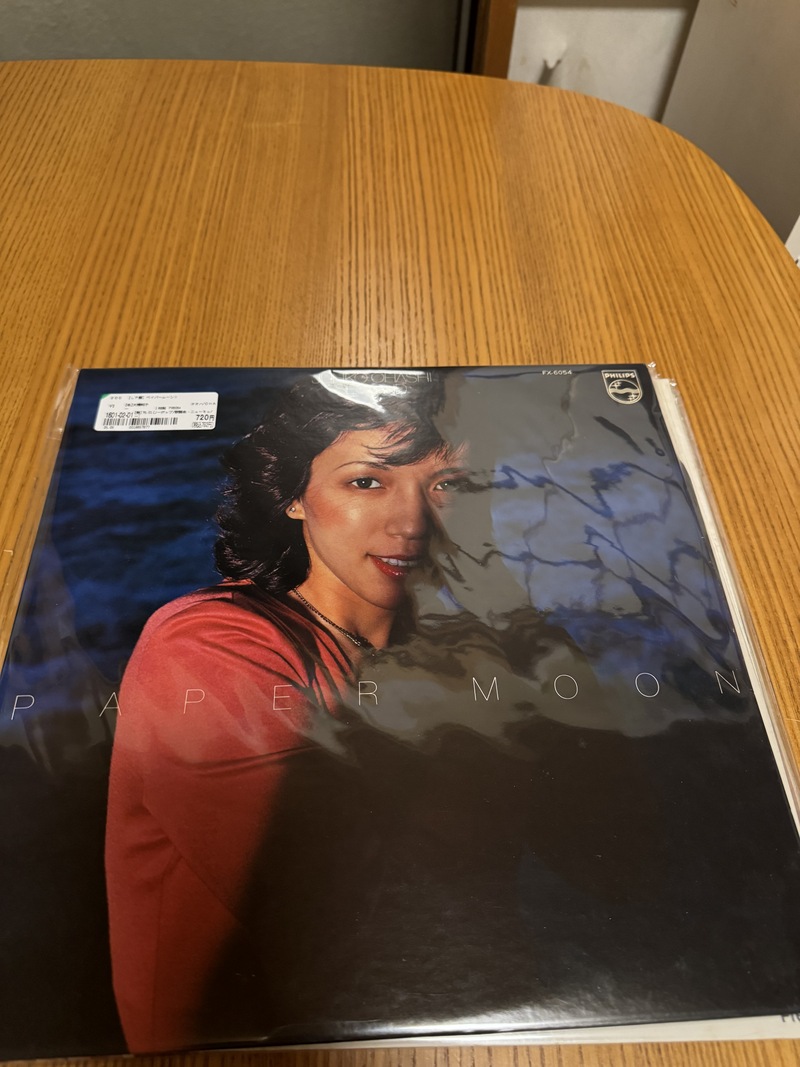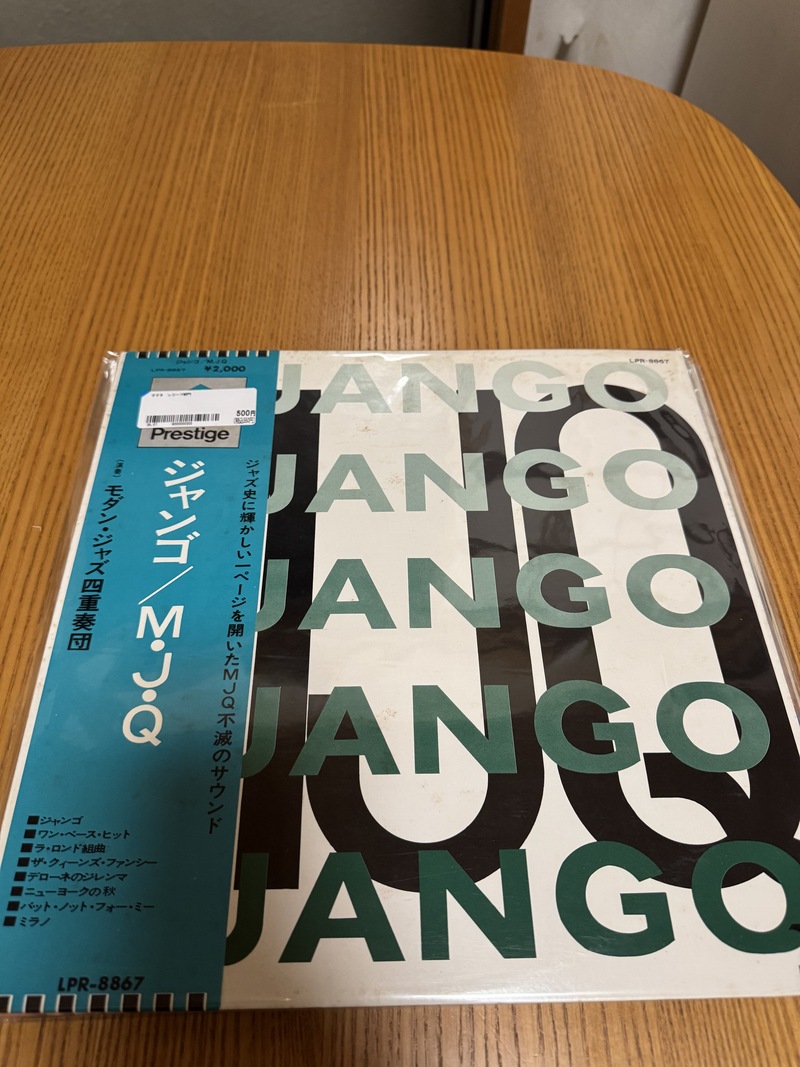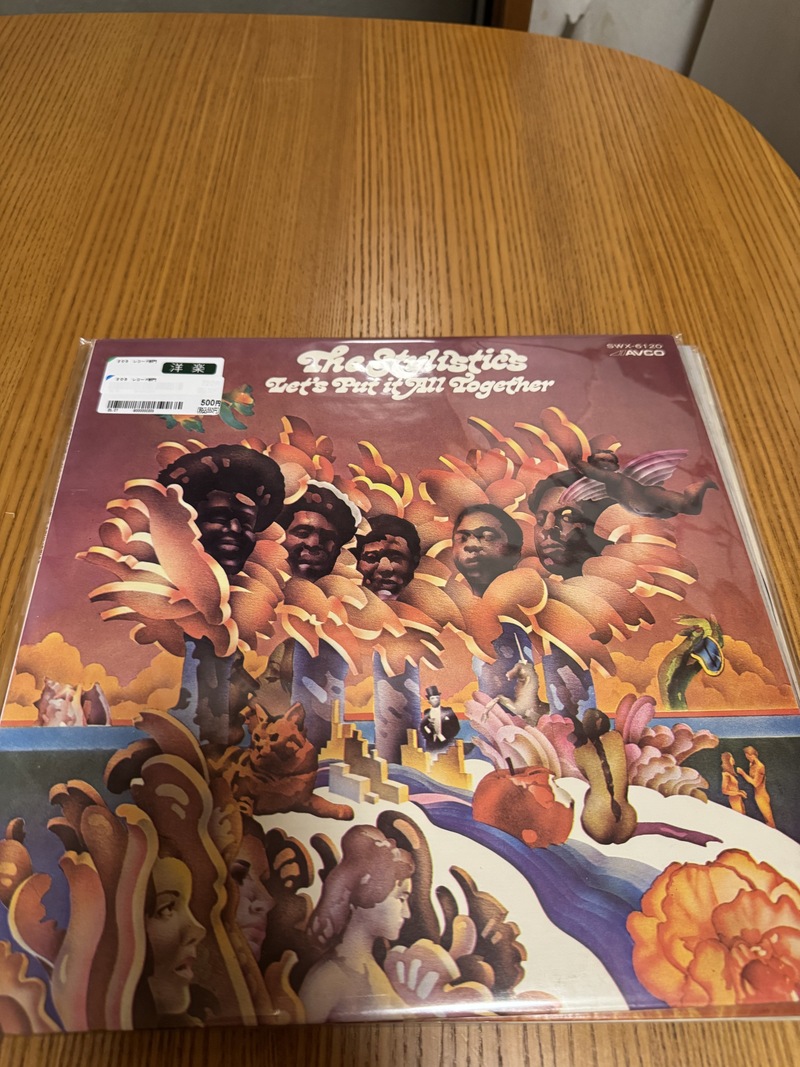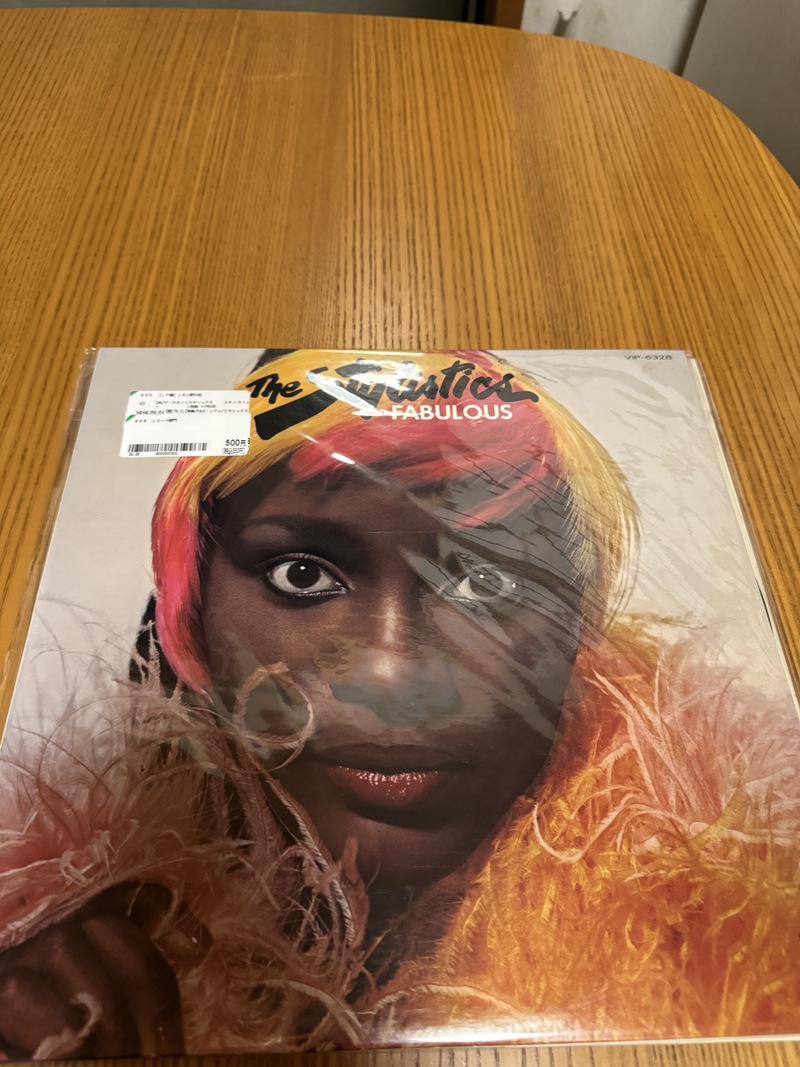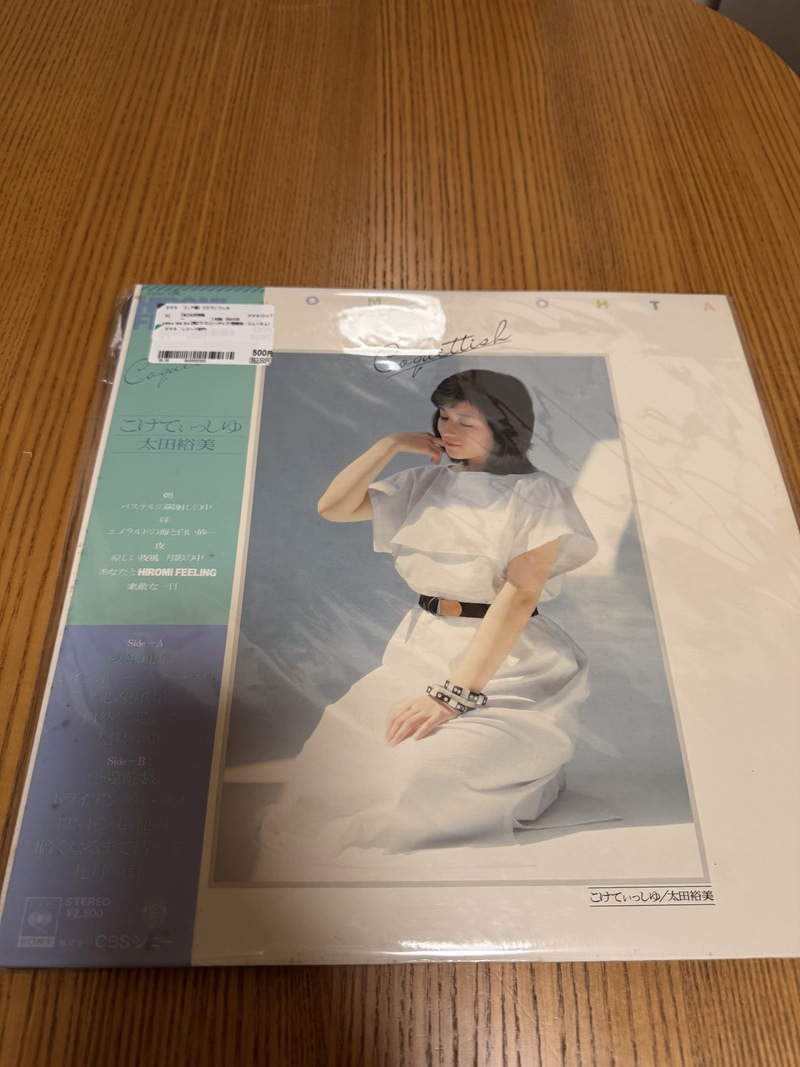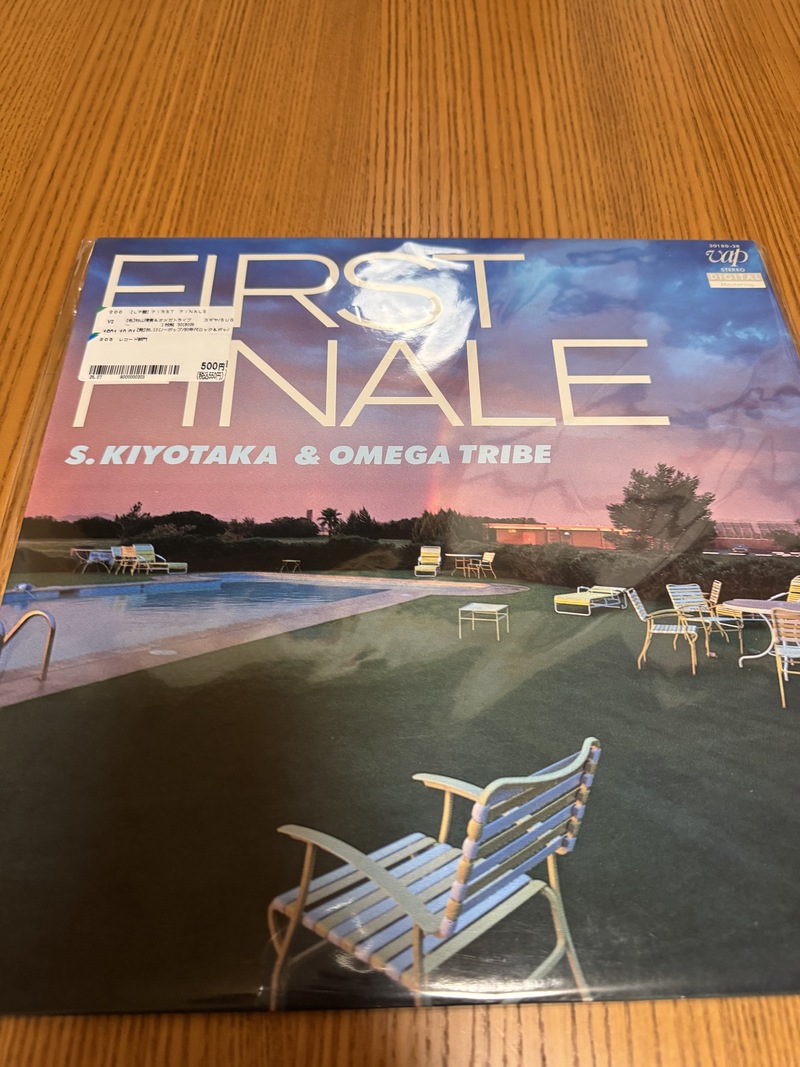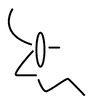こっちに戻ってきた。noteやQiitaなどは、もとの考えに戻して「他者を意識した記事だけを投稿する」ことにした。
早速品川区の粗大ゴミ申請を自動化する|コボリアキラ / Akira Koboriなんて投稿して、日記からは距離をとっている。
ObsidianとZettelkastenのことをあらためて考える一日だった
かなり単純化しすぎて考えていたかもなと反省し、もう一度基本というか、紹介されているナレッジやハウツーをもう一度噛み砕いてみようと思っている。また画像共有の仕方や文献メモのつくり方、一日の振り返り方など、個別の工夫も検討しなおしているところ。
日記を書かない間にも生成AIは進歩してきていて、株式投資についてはいよいよ「自分でつくったオリジナルのサービス」なんて不要になってきた。「◯◯について調べて」と言えば、スクリプトで取得したかった色んな定量的情報も、コーヒー片手にゆっくりと読むべき定性的情報も、どちらも4,5分で取得できる。
生成AIが出た当時からずっと思っているのは「これで試験学習ができるのでは」ということであり、いよいよそのタイミングが到達しそうだ。手始めに何をやってみようか考えたところ、FP3級がちょうどよさそうだなと思い、ちょっとやってみることにする。途中で飽きそうな気はするが、おそらく「こうやれば合格しそうだな」と思えるところまではやってみるつもり。
ロードマップを作らせてみたところ、
とあるので、これらをまとめてNotebookLMに突っ込んだうえで、
- NotebookLMを併用して学習する(ついでにObsidianにメモ作るとよさそう)
- 日々の学習ログを記録、できれば自動生成されるような仕組みにする
- そのためにNotebookLM上で学習しておきたい
- 学習ログをもとに次回以降の学習計画を更新する
みたいなことを検討中。まずは資料を用意したうえで、まず試験の概要を理解するところから始めてみようと思う。
※末尾にClaudeが提案した学習ロードマップを掲載している。
日記を書かない間にも東京女子プロレスは進歩してきていて、二度の海外興行の成功から明日は今年2つめのビッグマッチ。
どの試合も楽しみだけれど、やはり渡辺未詩・辰巳リカの白昼夢そして中島翔子・ハイパーミサヲの享楽共鳴によるプリンセスタッグ選手権試合がとくに注文の対象だ。四者四様と呼ぶべきか、本当に全員がいま自身のピークを更新しているところで、どちらが勝っても不思議でない。まったく想像がつかないが、その中でもミサヲさんが何を繰り出してくるかがとくに気になる。
また、推しの原宿ぽむ=ぽむちゃんが井上京子選手と組むのも楽しみすぎる。彼女のことだから、この降って湧いたおかしなチャンスは必ずモノにしてしまうだろう。ぽむちゃんの勝利にこそベットはできないが、ぽむちゃんの天才性とカリスマ性には全額注ぎ込める。
久々にさくらえみ選手を見れるのも楽しみで、それがまさかの”伊藤麻希&エル・デスペラード対さくらえみ&クリス・ブルックス”なんて組み合わせになるとは。デスペがセツナイロで踊り始めた瞬間、明日のチケット代は余裕でペイしたことになる。
もちろんメインイベントの瑞希対荒井優希も楽しみにしておこう。やはりチャンピオンのみずぴょん有利だという考えは変わらなかったけれど、そんな自分が「荒井ちゃんがベルト持つのもアリ…なのかも」と思うぐらい、前哨戦をふくむ3ヶ月感の荒井選手の成長が凄まじかった。東京女子のキラキラ感は好きだが、さすがに眩しすぎるほどに。
FP3級2025年9月試験に向けた、初回受験・1日30分未満・1.5か月準備の最適学習戦略をご提案します。あなたの基礎知識レベル(ライフプランニング、リスク管理、金融資産運用は理解済み)を考慮し、不動産・相続分野に重点を置いた効率的なプランです。
試験基本情報と最新動向
2025年9月試験はCBT方式による随時受験(9月1日-30日)で、学科試験時間が90分に短縮されています。合格基準は学科・実技ともに60%で、**日本FP協会の合格率は約85%**と高く、適切な対策により確実に合格可能です。
CBT方式の特徴として、コンピュータ画面での受験になるため、事前にCBT体験プログラムでの操作練習が必要です。また問題用紙の持ち帰りができないため、復習方法も従来と異なります。
最適学習戦略
核心となる3つの戦略
過去問中心アプローチが最も効果的です。FP3級は過去問からの出題が半数以上を占めるため、テキスト学習よりも過去問演習に時間の70%を割り当てます。
分野別重点配分では、あなたが不安な不動産・相続分野に全学習時間の45%(約20時間)を集中投下し、得意分野は効率的な復習にとどめます。
スキマ時間完全活用により、1日30分の制約を補完します。通勤時間や待ち時間を含めると実質的に1日45-60分の学習時間を確保できます。
教材選択の最適解
メインテキスト:「みんなが欲しかった!FPの教科書3級 2025-2026年版」(1,650円)
- フルカラー、CBT試験体験プログラム付き
- アプリ・動画特典で効率学習が可能
問題集:同シリーズの問題集(1,650円)で統一性を保つ
無料補強ツール:
- FP3級過去問道場:完全無料で3,000問収録、CBTシミュレータ付き
- ほんださん/東大式FPチャンネル:9時間で全範囲カバーのYouTube講義
総コスト:3,300円で市販教材としては最高のコストパフォーマンスを実現
詳細学習スケジュール
第1-2週(基礎固めフェーズ)
目標:既習分野の確認と不安分野の基礎構築
平日の学習リズム:
- 朝15分:前日の復習・暗記項目チェック
- 通勤時間:ほんださんYouTube講義(1.5倍速推奨)
- 昼または夜15分:テキスト読み込み・基礎問題
休日の集中学習:
- 土曜60分:不動産分野の重点学習
- 日曜60分:相続・事業承継分野の重点学習
週次目標:
- 第1週:全6分野のテキスト1周完了、YouTube講義4.5時間視聴
- 第2週:不動産・相続分野のテキスト精読、基礎問題演習
第3-4週(過去問演習フェーズ)
目標:過去問3回分の完全攻略、弱点の特定と補強
平日ルーティン:
- 朝15分:過去問1分野ずつの集中演習
- スキマ時間:FP3級過去問道場アプリで一問一答
- 夜15分:間違えた問題の解説確認・ノート作成
重点対策:
- 不動産分野:建ぺい率・容積率計算、借地借家法を完璧に
- 相続分野:法定相続分、相続税基礎控除額の計算を確実に
週次目標:
- 第3週:過去問2回分完了、正答率60%到達
- 第4週:過去問1回分追加、全分野正答率70%達成
第5-6週(仕上げフェーズ)
目標:模擬試験での安定した正答率確保、本番対策
最終調整:
- CBT模擬試験:本番環境での時間配分練習
- 弱点集中復習:これまでの間違い問題を重点的に
- 暗記項目の最終確認:数値・期間・計算公式
直前1週間の過ごし方:
- 新しい問題は避け、既習問題の反復のみ
- 1日20分程度の軽い復習で記憶を維持
- 十分な睡眠とリラックスを心がける
分野別攻略法
不安分野の重点対策
不動産分野(学習時間:12時間)
最重要計算問題:
建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
容積率 = 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100
重要暗記事項:
- 普通借地権:30年、定期借地権:50年以上
- 相続税路線価:公示価格の80%水準
- 固定資産税評価額:公示価格の70%水準
相続・事業承継分野(学習時間:8時間)
必須計算公式:
相続税基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
生命保険金非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人数
重要項目の優先順位:
- 法定相続人の範囲と順位(配偶者は常に相続人)
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分の多い方)
- 贈与税の基礎控除(年間110万円)
得意分野の効率復習
ライフプランニング・リスク管理・金融資産運用(各分野5時間)
過去問先行アプローチで、間違えた問題のみテキスト確認する効率重視の学習法を採用します。これにより短時間で確実な得点源を確保できます。
学習継続のコツ
エビングハウス忘却曲線の活用
科学的根拠に基づく復習タイミング:
- 学習直後:5分間の要点確認
- 24時間後:10分間の復習
- 1週間後:5分間の復習
- 2週間後:3分間の最終確認
モチベーション維持戦略
環境整備:固定学習場所の確保、スマホ学習環境の最適化
進捗管理:Studyplusアプリで学習時間の可視化
報酬システム:週目標達成時の小さなご褒美設定
試験直前対策
最後の2週間でやるべきこと
模擬試験の実施:CBT形式で本番同様の90分間
弱点の最終確認:間違いノートの総復習
暗記項目チェックリスト:数値・期間・計算公式の最終確認
試験当日の準備
持参するもの:顔写真付き身分証明書のみ(受検票は廃止)
到着時刻:試験開始30分前
メンタル準備:60%合格の試験なので、完璧を求めず確実に解ける問題に集中
成功への最終アドバイス
この学習プランの成功率を最大化するために、継続性を最重視してください。完璧を目指さず、毎日少しずつでも学習を続けることが合格への確実な道です。
あなたの基礎知識を活かし、不安分野に集中投資することで、限られた時間でも十分に合格ラインを突破できます。FP3級の85%という高い合格率は、適切な対策により誰でも合格可能であることを示しています。
最後に重要なポイント:試験申し込みは早めに済ませ、具体的な試験日を決めることで学習計画の実行力が飛躍的に向上します。
このプランに沿って着実に学習を進めれば、2025年9月のFP3級試験合格は確実に達成できるでしょう。