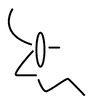文字通り「新書」だと思って購入したところ、1988年の発行だと知り、驚いた。まだ自分が生まれるギリギリ前に、このような名著が出ていたとは。
[amazonjs asin=“4061488988” locale=“JP” title=“はじめての構造主義 (講談社現代新書)“]本書は、80年代当時流行っていた、そして今でも影響を与えている <構造主義>という思想について、どのように出来上がってきたかを解説したものだ。学術書としては平易に書かれているため、読みやすい。 <構造主義>の産みの親とも言えるレヴィ=ストロースに注目している点が特徴的だ。彼の仕事を追うように進むので、まるで自分が構造主義を考えたかのような気持ちになれる。だから、読んでいて違和感が無い。あまりにストレートなので、むしろ疑いの念が生まれる。
レヴィ=ストロースは人類学・神話学の学者で、自分の興味の範疇に入っている。はずなのだが、実際に思想に触れたことは無かった。同じような人には、強くオススメしたい。
本書を読んでとくに面白かった点は、2つある。 ひとつは、<構造主義>あるいは<構造主義>を形作った思想や学問があらゆる ヨーロッパ文明(マルクス主義、実存主義、機能主義、ユークリッド幾何学、作者の権威、主体の価値、ただひとつの真理) を内部からブチ壊していったこと。この流れが気持ちよく書かれている。
とくに、<構造主義>は「理性」と「真理」に対するヨーロッパの盲目な信頼に大打撃を与えた。何千年もかけて求めた真理に対して、 「唯一の真理は無い」
という答えを出してしまったのである。
ここでの重要な点は、この答えが別の異世界からもたらされたものではないことだ。ヨーロッパ文明が発展を遂げていく中で生まれた自己修正なのである。
もうひとつの面白かったところは、上のような思想が、実は 数学を下地としていた ことだ。 以降では、こっちの話をちょっとまとめておきたいと思う。
数学は絶対でない
長い歴史の中で、さまざまな思想が生まれては消え、更新されていったヨーロッパ文明。しかし、その中で変わらないものがあった。それは 「真理」 だ。
どんな考えも思想も、この「真理」に対するアプローチであることに変わりはない。思想家たちは真理を求めて、さまざまな考えを打ち出したのである。
この「真理」へと辿るレールを整備したのは、数学の 証明 (と論理学)だった。
この手法を使えば、途方も無い時間はかかるかもしれないが、間違いなく一歩ずつ真理へと進められる、とヨーロッパ文明は考えていた。
数学の証明とは、「公理から定理を導き出すこと」だ。詳しく説明すれば、
「論理とかじゃなく、どう考えたって正しいこと」をスタートにして、「論理的に導き出せる答え」を作ろう 、という感じ。
ポッキーの先端(公理)を食べ始めると自然ともう片方の先端(定理)までたどり着く、みたいなイメージだとわかりやすいだろうか。
このとき、ポッキーの先端は証明不可能(ここが重要)であり、証明の必要も無いくらいに正しいのである。
2000年前につくられた「ユークリッド幾何学」がこれにあたる。「直線外の一点を通って、その直線に平行な直線を一本だけ引くことができる(平行線定理)」など、5つの公理が定められた考え方だ。
しかし19世紀に入ると、この考え方に並ぶ考え方が現れる。「非ユークリッド幾何学」である。
非ユークリッド幾何学の誕生は、とてつもない衝撃を生み出すことになった。それは、 非ユークリッド幾何学の公理が、ユークリッド幾何学の公理と異なるからである。 つまり、「論理とかじゃなく、どう考えたって正しいこと」が2つあったのだ。 ポッキーは1本じゃなかったのだ!
これは、数学以外の思想にも大きな影響を与えることになる。今までに導き出していた真理は、すべてある任意の公理から作られているだけなのではないか。別の公理を設定すれば、まったく異なった真理が出てくるのではないか。
<構造主義>では、この公理のことを「制度」と呼び、
「ヨーロッパの知のシステムは、<真理>を手にしていたつもりで、実は制度の上に安住していただけではないか」 (本書p152)との批判を提出した。
ちなみにこのあとの数学は、非ユークリッド幾何学を皮切りに、リーマン幾何学、ロバチェフスキー・ボーヤイの幾何学など様々な公理をもとにした幾何学が生まれ、20世紀にはアインシュタインによるユークリッド幾何学から遠く離れたモデルを利用した理論(相対性理論)まで生まれることになった。
本書の説明はここで終わらず、実はこのあとの 「<構造>は、<遠近法>の発展の末に生まれた」 という仮設がもっともスリリングで面白い。
結論部しか引用しないのでわかりづらいとは思うが、興味があれば読んで損は無いと思う。ぜひ。
レヴィ=ストロースは、主体の思考(ひとりひとりが責任をもつ、理性的で自覚的な思考)の手の届かない彼方に、それを包む、集合的な思考(大勢の人びとをとらえる無自覚な思考)の領域が存在することを示した。それが神話である。神話は、一定の秩序――個々の神話の間の変換関係にともなう<構造>――をもっている。この<構造>は、主体の思考によって直接とらえられないもの、“不可視”のものなのだ。
(橋爪大三郎『初めての構造主義』、講談社現代新書、1988年、p190。)